ホウレンソウは、家庭菜園初心者にも人気の高い葉物野菜です。寒さに強く、畑での栽培では、土づくりや水やりのコツをつかむことで、より濃い緑色の美味しいホウレンソウを育てられます。
本記事では、家庭菜園でホウレンソウを上手に育てる方法を、初心者にも分かりやすく解説します。

芽出しと種まきについて
ステップ1 時期と気温を決める
ホウレンソウは涼しい気温を好みます。地温が15〜20℃前後になる秋口から初冬、または早春が最も育てやすい時期です。25℃を超えると発芽が不安定になりやすいので、まだ暑さが残る日は夕方に作業すると落ち着いて芽が動きます。日当たりの良い畑を選び、半日程度は直射日光が当たる場所がおすすめです。
ステップ2 畑の土づくりを整える
よく耕して、ふかふかの土にします。水はけと水もちのバランスが大切なので、堆肥を入れて土に空気の通り道を作ります。酸性に弱いので、土が酸っぱめなら苦土石灰を種まきの1〜2週間前に混ぜて中和しておきます。畝は幅60〜80cm、表面を平らに均しておくと均一に発芽します。
ステップ3 やさしい芽出し下ごしらえ
発芽をそろえたい場合は、乾いた種をぬるま湯に6〜12時間ほど浸けて水を含ませます。水を切ったら、湿らせたキッチンペーパーに包み、15〜20℃の室内で1日ほど置きます。白い芽が少し顔を出しかけたら播きどきです。気温が高い時期は冷蔵庫の野菜室で半日ほど冷やしてから播くと落ち着いて発芽します。扱いはやさしく、こすらずに手のひらで転がすようにすると傷みません。
ステップ4 すじまきで均一に播く
畝の表面を軽く押さえて細かな凹凸をならします。深さ1〜1.5cmの浅い溝を20〜25cm間隔で引き、芽出しした種を指先でつまんで1〜2cmおきに落としていきます。密になりすぎると徒長しやすいので、気持ちゆったりめを意識します。覆土はふるった細土を薄くかけ、最後に手のひらでぽんぽんと軽く押さえて種と土を密着させます。
ステップ5 発芽までの水分管理と保護
播種後はじょうろで細かい水をたっぷり与え、表面が乾きやすい場合は朝と夕の二度水やりします。乾燥と鳥害を防ぐために不織布をふんわり掛けると安心です。土がびしょびしょになると酸欠で芽が弱るので、水たまりができない程度に調整します。順調なら4〜7日ほどで芽がならんで顔を出します。
ステップ6 本葉が見えたら間引きと追肥
双葉が開きそろったら、株同士が触れない程度に軽く間引きます。本葉2〜3枚で最終的に株間5〜7cmを目安に整えると太く短い良い株に育ちます。生育の勢いが落ち着いて見える頃、畝の片側に浅い溝を切って化成肥料をごく少量すじ状に入れ、土を戻して水やりします。ゆっくり効く有機肥料を株元から少し離して土に混ぜるのもおすすめです。肥料はかけすぎず、葉色が淡くなったときに控えめに足すのがコツです。
ステップ7 立ち上がりを見守る環境づくり
本葉が増え始めたら、朝のうちに軽く水を与え、午後は風通しを確保して蒸れを避けます。表土が固くなってきたら株を傷めないよう浅く中耕して空気を入れます。夜の冷え込みが強い時期は不織布を続けると葉先の傷みを防げます。順調なら種まきから30〜45日ほどで、葉がつややかに立ち上がり、やわらかな収穫どきへ向かいます。

マルチングについて
ステップ1 マルチの役割を知る
マルチングは、土を覆って乾燥や雑草を抑え、泥はねや寒さから株を守る作業です。ホウレンソウは浅い根で乾きに弱いので、水分を保つ効果がよく効きます。秋冬どりなら地温を少しだけ保てるので、生育のムラも減り、葉が汚れにくく収穫後の下処理が楽になります。
ステップ2 選ぶ素材を決める
扱いやすさ重視なら黒いビニールマルチが便利です。地面をしっかり覆えて雑草を強く抑えます。環境になじむ方法なら、ワラや落ち葉、細かく刻んだ枯れ草などの有機マルチが向きます。不織布は保温と風よけも兼ねられ、寒さが厳しい地域で重宝します。迷ったら、畝には黒マルチ、株上には不織布という組み合わせが扱いやすいです。
ステップ3 張るタイミングを合わせる
黒マルチは種まきの前に畝へピンと張ります。土を十分に湿らせ、表面を平らに均してから使うとたるみません。地温が上がり過ぎる時期は避け、涼しくなってから作業します。有機マルチは発芽を妨げないよう、すじまき後に芽が出そろってから薄く敷くと安心です。厚く敷きすぎると芽が光と空気を得られず弱るので注意します。
ステップ4 穴あけと間隔を整える
黒マルチにする場合は、直径3〜4cmの穴を作り、列間は20〜25cm、株間は5〜7cmを目安にします。ホウレンソウは込み合うと細長くなりやすいので、最初から少しゆとりを持たせます。すじまき派は、種の列の真上に細長い切り込みを入れる方法でも大丈夫です。いずれも風でばたつかないよう、端をしっかり固定します。
ステップ5 水やりと温度の様子を見る
発芽までは表土が乾かないように、じょうろで細かい水を与えます。マルチは蒸発を抑えるため水持ちがよく、与えすぎると過湿になりやすいので、表面の色と手触りで加減します。日中に葉がぐったりし、夕方に回復する程度なら水分は足りています。黒マルチで日差しが強い日は温度が上がるため、不織布を少し浮かせて通気を確保すると安心です。
ステップ6 雑草と追肥を上手にこなす
マルチがあると雑草はぐっと減りますが、穴の周りから出ることがあります。小さいうちに指で抜き、土を軽く寄せて光を遮ります。生育が落ち着いた頃、畝の端からマルチを少しだけめくり、溝を切って化成肥料を控えめにすじ状に入れて土を戻します。ゆっくり効く有機肥料を株元から離して土になじませるのもおすすめです。与えた後は株元に水を通し、マルチを元どおり密着させます。
ステップ7 季節に合わせて使い分ける
秋冬は黒マルチで保温しつつ、不織布をトンネル状にかけると霜や冷たい風から葉を守れます。早春は晴れた日にトンネルの裾を少し上げて換気し、蒸れを防ぎます。有機マルチは厚みを指一本分程度に保ち、雨で薄くなったら軽く足して調整します。収穫期が近づいたら通気をよくし、朝に軽く水を通すと葉が締まり、つやよく育ちます。マルチを味方につければ、手間を減らしながら安定して美しい株に仕上がります。

栽培管理について
ステップ1 日当たりと風通しを整える
ホウレンソウは涼しくて日当たりのよい環境が好きです。畝の表面を固めないように時々くわ先で浅くほぐし、株の周りに空気を通します。密植は蒸れの原因になるので、葉が触れ始めたら迷わず間引き、株間5〜7cmを目安にそろえます。風が通るだけで病気の発生がぐっと減り、葉も厚く締まります。
ステップ2 水やりは朝に控えめ、乾きすぎは防ぐ
根が浅いので乾燥には弱い一方、過湿も苦手です。基本は朝に土の表面が白っぽく乾いたら与える程度にします。指で2〜3cm掘ってひんやりしていればまだ大丈夫です。雨の翌日は水やりを休み、畝のわきに溝を切って余分な水を逃がします。夕方のたっぷり水やりは夜間の蒸れにつながるので避けます。
ステップ3 間引きと土寄せで株を安定させる
本葉2〜3枚で混み合った株を抜き取り、元気な株だけを残します。間引いた後は株元に軽く土を寄せて、根が揺れないよう支えます。表土が硬くなっていたら浅く中耕して、細い割りばしがすっと入る程度にほぐします。これだけで根の呼吸が良くなり、葉色がぐっと濃くなります。
ステップ4 生育の合図を見て追肥する
葉色がやや薄くなり生長がゆっくりに感じたら、畝の片側に浅い溝を作り、化成肥料をごく控えめにすじ状に入れて土を戻します。肥料は株元に直接触れないよう少し離して施します。ゆっくり効く有機肥料を土とよくなじませておくと、収穫期まで安定して育ちます。与えすぎは葉がやわらかく伸びすぎる原因になるので、少量で様子を見るのが安心です。
ステップ5 病害虫は早期発見と環境づくりで防ぐ
葉裏に集まるアブラムシや、葉に細い白い筋を残すハモグリバエは、見つけ次第、被害葉を摘み取り畑の外で処分します。葉がいつも濡れている状態は病気を呼ぶため、株元灌水を心がけます。風通しを良くし、古い下葉は黄変前に外しておくと、ベと病などの発生が抑えられます。畝間に不要な葉や雑草を残さないことも効果的です。
ステップ6 温度と日長を味方につけてとう立ち予防
高温や長日で花芽がつくとう立ちが進みます。春先に気温が上がってきたら、日中は不織布トンネルの裾を上げて換気し、地温の上がりすぎを防ぎます。初秋の残暑が強いときは、午後だけ寒冷紗で軽く日よけをして温度を緩めます。育ちが止まるほどの低温が続く場合は、夜だけ不織布でふんわり保温すると生長が途切れません。
ステップ7 仕上げの管理でおいしさを高める
収穫の2〜3日前は水を控えめにして、葉の水分過多を防ぎます。朝のうちに軽く水を通す程度にとどめると、葉が締まって扱いやすくなります。泥はねが気になる場合は株元に薄く土を寄せて葉を持ち上げるときれいに育ちます。外葉が大きく開き、中心の若い葉がしっかり立ってきたら、味と香りの乗った収穫どきが近い合図です。丁寧な日々の管理が、そのまま一口目の濃い味わいにつながります。

追肥について
ステップ1 追肥のねらいを知る
ホウレンソウは短期間でぐっと育つため、途中で少しだけ栄養を足してあげると、色つやが良くなり、葉が厚く締まります。最初に入れた元肥を土台に、必要なときに必要な分だけそっと補うのがコツです。入れすぎは葉が軟らかく伸びすぎたり、味がぼやけたりするので控えめを心がけます。
ステップ2 与えるタイミングを見極める
双葉がそろい、本葉が2〜3枚になった頃が最初の目安です。その後は生育の勢いが落ちたと感じたとき、または葉色が淡くなってきたときに検討します。冷え込みの強い朝夕や強い日差しの下は避け、昼前後の穏やかな時間に行うと株への負担が少なくて済みます。
ステップ3 量は少なめ、場所は株から離して
化成肥料は畝の片側に浅い溝を切り、すじ状にごく薄く落として土を戻します。目安は1メートルあたり小さじ2〜3程度から始め、様子を見て必要ならもう一度にとどめます。株元に触れると根を痛めるので、指二本分ほど離して施します。与えた後は軽く水を通して、肥料を土になじませます。
ステップ4 ゆっくり効かせる選択も考える
畝の表面を軽くほぐし、株元から少し離した位置に、有機肥料を少量混ぜ込む方法も穏やかでおすすめです。効き方がゆるやかなので、天候が安定しない時期や、急に伸ばしたくない場面でも扱いやすく、葉が締まりやすくなります。においが気になる場合は、しっかり土で覆ってから水を通すと落ち着きます。
ステップ5 季節と天気に合わせて微調整する
秋冬どりでは低温で効きがゆっくりになるため、少量をこまめに補うと安定します。晴天が続いた後は土が乾いて効きが立ちやすいので、いつもより控えめに始めます。雨の直前に施すと溶け出しやすく効きが偏るため、雨上がりに土の表面が落ち着いてから与えるとムラを防げます。
ステップ6 葉のサインを読み取る
全体の葉色が淡く、葉が細長くなってきたら不足の合図です。一方、濃い緑で軟らかく徒長気味なら与えすぎのサインかもしれません。その場合は追肥を一度休み、軽く中耕して土に空気を入れ、朝だけの控えめな水やりに戻します。数日で姿が落ち着けば、その後の追肥も減らして進めます。
ステップ7 収穫前の仕上げを意識する
収穫が近づいたら、新たな追肥は控えめにし、葉を締める管理に切り替えます。与える場合もごく少量に抑え、株から離した位置に薄く施して土を戻します。数日かけてゆっくり効かせ、収穫の2〜3日前は水も多く与えすぎないようにすると、香りが立ち、歯切れの良い仕上がりになります。丁寧に様子を見ながら少量で積み上げることが、味わいのよいホウレンソウへの近道です。

プランターでの栽培方法
ステップ1 容器と土を整える
深さ20cm以上、幅60cmクラスのプランターが扱いやすいサイズです。底穴にネットを敷き、軽石を2〜3cm入れてから野菜用培養土を入れ、縁から下2〜3cmを残して軽くならします。土は押し固めず、手のひらで表面をそっと平らにします。日当たりと風通しのよい場所を選び、強風が直撃する場合は壁際に寄せて風当たりを和らげます。培養土は中性寄りが向き、pHはおおむね6.0〜7.0を目安にします。
ステップ2 種まきの下ごしらえ
表面を平らにして、深さ1〜1.5cmの浅い溝を2本作ります。列の間隔は15〜20cmが目安です。種は1〜2cmおきに落として薄く覆土し、手のひらでぽんぽんと軽く押さえて土と密着させます。残暑がある時期は午後遅めに播くと地温が落ち着き、発芽がそろいやすくなります。気温が高い日は、播種後にプランターを半日陰へ移して初期の乾きすぎを防ぎます。
ステップ3 発芽までの水分管理
じょうろのハス口で細かい水をたっぷり与え、表面が乾きやすいときは朝夕の2回に分けます。受け皿に水をためっぱなしにすると根が傷むため、与えた水が鉢底から抜けたら受け皿は空にします。直射が強い日は午前は日なた、午後は明るい日陰に寄せると過度の乾燥を避けられます。順調なら4〜7日ほどで列になって芽が上がります。
ステップ4 間引きと株間の調整
双葉が開いたら重なった芽を外し、株同士が触れない程度に間引きます。本葉2〜3枚で株間5〜7cmまで整えると、太く短くしまった株に育ちます。間引き後は株元に軽く土を寄せ、表土が固い場合は割りばしで浅く筋を入れて空気を通します。間引き菜は若どりで食べられるので、抜き過ぎをためらわずリズム良く整えます。
ステップ5 水やりと置き場所のコツ
基本は朝に、表面が白っぽく乾いたタイミングで鉢底から少し流れ出るくらい与えます。日中に一時的にぐったりして夕方に戻る程度なら水分は足りています。連日の強い日差しやベランダの照り返しが厳しい日は、午後だけ半日陰へ移すと葉先の傷みを防げます。雨天や台風前は屋根のある場所へ移動し、用土が過湿にならないようにします。
ステップ6 プランター向けの追肥と病害虫対策
生長の勢いが落ちたり葉色が淡くなってきたら、プランターの縁沿いに化成肥料をごく少量、指先でつまむ程度から置いて土と軽く混ぜます。株元には触れない位置に施し、その後は軽く水を通してなじませます。ゆっくり効く有機肥料を少量、縁側に混ぜ込む方法も穏やかで扱いやすいです。葉裏のアブラムシや、葉に白い筋を残す食害を見つけたら、被害葉を摘み取り速やかに処分します。枯れ葉はこまめに外し、鉢の周りに落ち葉を溜めないだけでも発生はぐっと減ります。

農薬サイクルの考え方
ホウレンソウは生育が早く、収穫までの期間が短い作物です。病害虫は「出てから慌てる」より「出にくくする」ことが大切です。まずは発芽直後から風通しと乾湿のメリハリを意識し、予防と観察をセットにします。そのうえで、同じ成分を続けない「サイクル散布」を組み、効き目が落ちる(薬剤耐性がつく)リスクを減らします。ここでは家庭菜園でも入手しやすい製品名(代表例)と成分を挙げたサイクル例をご紹介します。製品の適用作物・使用回数・希釈倍率・収穫前日数は必ず手元のラベルで最終確認してください。
ホウレンソウの害虫・ダニ防除サイクル例
【害虫・ダニの農薬サイクル(共通)】
ホウレンソウの害虫はアブラムシ、ヨトウムシ類、ハモグリバエ、まれにダニ類が中心です。発生初期をねらい、観察→必要量だけ散布→記録の順に進めます。
ホウレンソウの害虫・ダニ防除サイクル例
| 散布時期 | 使用農薬(成分) | 対象 | 散布間隔の目安 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 発芽直後〜本葉2枚(予防寄り) | デルフィン顆粒水和剤(BT菌:バチルス・チューリンゲンシス) | ヨトウムシ・チョウ目幼虫 | 7〜10日 | 食害穴が出る前の予防兼初期対応。天敵にやさしい。 |
| 本葉3〜4枚、アブラムシ見え始め | モスピラン顆粒水溶剤(アセタミプリド) | アブラムシ | 10〜14日 | 葉裏へ丁寧に。系統が異なる薬と交互に。 |
| その10日前後後、被害継続時 | スピノエース顆粒水和剤(スピノサド) | ヨトウムシ・ハモグリバエ | 7〜10日 | 食入前の幼虫期が狙い目。BTと交互使用で効果安定。 |
| 高温期に葉裏ダニが気になるとき | コロマイト乳剤(ミルベメクチン) | ダニ類 | 14日 | ダニ専用。必要時のみ点状散布で十分。 |
| アブラムシ再発時の持続対策 | プレオ20フロアブル(クロラントラニリプロール) | チョウ目幼虫 | 10〜14日 | 作用機構が異なるためローテーションに組み込みやすい。 |
| 収穫2週間前目安、仕上げ | ベニカXファインスプレー(アセタミプリド+ペルメトリン系などの家庭園芸用複合剤) | 広範囲の害虫 | ラベル指示 | 収穫前日数を必ず確認。仕上げの部分使いにとどめる。 |
※出来るだけ違う農薬でサイクルするようにしてください
※あくまでも参考例としてご覧ください
ホウレンソウの病気防除サイクル例
【病気の農薬サイクル】
病気はとくにベト病(葉が黄色く角張って抜けるように変色)とうどんこ病が要注意です。予防と初期発見が決め手になります。
ホウレンソウの病気防除サイクル例
| 散布時期 | 使用農薬(成分) | 対象 | 散布間隔の目安 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 発芽直後〜本葉2枚、雨前の予防 | ランマンフロアブル(フルアジナム) | ベト病 | 7〜10日 | ベト病予防の定番。雨の前に先回り散布が効果的。 |
| 生育中期、病斑の出始め | アミスター20フロアブル(アゾキシストロビン) | うどんこ病・葉枯れ類 | 10〜14日 | 作用機構が異なるためローテーションに入れやすい。 |
| 高湿続きで再発が心配 | カリグリーン(炭酸水素カリウム) | うどんこ病 | 7日 | 食酢系より安定。仕上がり洗浄もしやすい。 |
| 低温多湿期、症状前の差し込み | Zボルドー水和剤(硫酸銅・石灰ボルドー) | ベト病・斑点性病害 | 10〜14日 | 薬害を避けるため薄め・涼しい時間帯に限定。 |
| 苗立枯れの予防(播種前処理) | タチガレン液剤(エトリダゾール) | 苗立枯れ(ピシウム) | 1回(床土処理) | 播種床の一次予防。栽培中の散布ではなく用土処理用。 |
※出来るだけ違う農薬でサイクルするようにしてください
※あくまでも参考例としてご覧ください
使い方のステップ(初めてでも迷わない進め方)
最初に栽培カレンダーを1枚用意し、播種日と収穫予定日を書き込みます。次に、上の表から「予防→初期対応→別系統」の順に3〜4種類を選び、同じ成分が続かない並びにします。週1回の観察日を決め、葉裏・葉柄の付け根・外葉の縁を必ず見ます。発生が軽微ならまずは物理的除去(指でつぶす、被害葉を外す)を優先し、薬剤は「必要なときに必要な場所へ」を合言葉にポイント散布から始めます。散布した日、薬剤名、希釈倍率、天気、症状の変化をノートに残すと次回判断が格段に楽になります。
農薬散布に関する注意事項(使用回数・安全日数・散布時の注意・保管)
使用回数はラベルで作物別に定められています。ホウレンソウに使える回数を超えないよう、サイクル表の横に「残り回数」を書き足して管理すると安心です。収穫までの日数に余裕がないときは、収穫前日数(安全日数)が短い製品や、物理・生物由来の薬剤を優先します。安全日数は製品ごとに違うため、散布前に必ず確認してください。
散布は風の弱い朝夕の涼しい時間に行い、葉裏まで均一に薄い霧で当てます。希釈は台所ではなく屋外で行い、計量スプーンやカップは農薬専用にします。マスク、手袋、長袖を着用し、散布後は手洗い・うがいを丁寧に行います。周囲に小さな子どもやペット、ハーブなど収穫間近の作物がある場合は、養生してから始めます。
余った薬液は保管せず、その日のうちに使い切ります。原液や粉剤は直射日光と高温多湿を避け、鍵のかかる棚で立てて保管します。ラベルと計量具を同じ箱にまとめると、希釈ミスの防止に役立ちます。古い薬剤やラベル不明の容器は使用しないでください。
無農薬(薬剤不使用)で育てたいときのコツ
播種直後から不織布のベタがけや0.6〜1.0mm目合いの防虫ネットで物理的に侵入を防ぎます。畝と畝の間は常に乾いた通路を保ち、株間はやや広めにして風通しを確保します。朝のうちに灌水し、夕方には葉が乾くリズムをつくるとベト病が出にくくなります。黄色や青の粘着プレートを設置し、飛来害虫のモニタリングと捕獲を同時に行います。被害葉は見つけ次第その場で取り除き、周辺の雑草はこまめに抜いて虫の隠れ家を減らします。前年に病気が出た場所は同じホウレンソウや近縁のヒユ科野菜を避け、2〜3年の輪作を心がけます。最後に、耐病性表示のある品種を選ぶことも強い味方になります。
仕上げのひとこと
ここに挙げた製品名は入手しやすい一例です。必ずお手元のラベルで「ホウレンソウに適用があるか」「使用回数・希釈倍率」「収穫前日数」を確認してから使ってください。サイクル散布と毎週の観察を組み合わせれば、家庭菜園でも安定してきれいな葉を収穫できます。気持ちよく育てていきましょう。
収穫について
ステップ1 収穫どきの見極め
草丈が20〜25cmほどになり、外葉がよく開いて中心の若い葉がまっすぐ立ってきたら食べごろです。葉柄がほどよく太り、葉の縁がぴんと張っている状態が合図になります。秋冬まきなら種まきからおよそ30〜45日、春の気温が高い時期は20〜30日がひとつの目安です。葉色が濃く、手でそっと触れて弾力を感じたら味の乗りやすいタイミングです。
ステップ2 収穫前日の準備と当日の時間帯
前日は水を控えめにして、当日は朝の涼しいうちに行うと、葉が締まって扱いやすくなります。露が乾き始める頃が最適で、土も適度に落ちやすくなります。はさみや包丁は刃先をきれいにしてから使い、切り口の傷みを減らします。マルチや不織布を使っている場合は、作業前にそっと外して風を通し、株を落ち着かせます。
ステップ3 株ごと抜き取る方法
株元の土を指で軽くほぐし、片手で地際を支えながら株を前後に小さく揺すって根を緩めます。反対の手で葉をまとめ、まっすぐ上へ引き上げると折れにくく抜けます。抜いたら根に付いた土を手でやさしく払っておきます。粘土質で土離れが悪いときは、細いスコップを株元の横から差し入れ、根を傷めない角度でてこのように持ち上げるとスムーズです。
ステップ4 外葉だけをかき取る方法
長く楽しみたい場合は、外側の大きな葉から数枚ずつ切り取ります。中心の若い葉と生長点は残し、地際から少し上の位置で斜めにカットします。切り口に泥がつかないよう、先に株元の土を少し寄せて葉を持ち上げてから切ると清潔に保てます。株の負担を軽くするため、同じ株は数日あけてから次の収穫にします。
ステップ5 ベビーリーフのタイミング
やわらかい食感を狙うなら、草丈10〜15cmで若どりします。密植気味にまいた場所を間引きながら収穫すると、残した株に光と風が入り、その後の育ちも安定します。若どりを続けるときは、株元を深く切りすぎず、葉柄の根元を少し残すと新しい葉が上がりやすくなります。
ステップ6 収穫後の下処理と洗い方
畑やプランターの脇で大きな泥を軽く払ってから、キッチンで根を切り分けます。大きめのボウルにたっぷりの水を張り、葉を泳がせるように振り洗いすると砂が落ちやすく、こすらないので葉を傷めません。茎の根元に薄く切れ目を入れて開くと中の砂抜けがよくなります。洗った後はざるで水を切り、清潔な布で軽く押さえて余分な水分を取ります。
ステップ7 保存とおいしさの保ち方
すぐ使わない分は、茎の根元を湿らせたキッチンペーパーで包み、軽く口を開けた保存袋に入れて野菜室で立てて保管します。目安は2〜3日で、時間がたつほど香りが落ちやすいので早めに使い切ると風味が生きます。長めに保存したい場合は、さっと湯通しして冷水で急冷し、水気をよく絞って小分けにして冷凍します。凍ったまま加熱料理に使うと食感が保たれます。収穫の前後で水のやり過ぎを避け、涼しい時間帯に手早く扱うだけで、色つやと香りがぐっと引き立ちます。

最後に
ホウレンソウ栽培は、少しの手間でぐんと成長してくれる、家庭菜園の頼もしい相棒です。日当たりのよい場所を選び、ふかふかの土をつくるところから始めれば、初めての方でも十分に立派な株を育てられます。種をまいてから毎日少しずつ葉が大きくなっていく姿は、まるで季節の移ろいを感じさせてくれる小さな自然のドラマのようです。寒さに強いホウレンソウは、秋から冬の畑を鮮やかな緑で彩り、朝霜の中でも凛と立ち続けます。収穫の瞬間に手のひらで感じるみずみずしさ、そして自分で育てた葉を食卓にのせたときの甘みと香りは、何度味わっても感動します。畑に出る時間が少しの癒しとなり、日々の暮らしに彩りを添えてくれる──そんな楽しさが、ホウレンソウづくりには詰まっています。



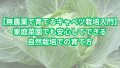

コメント